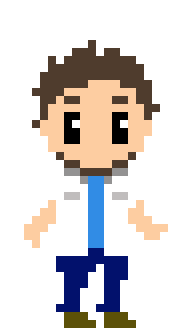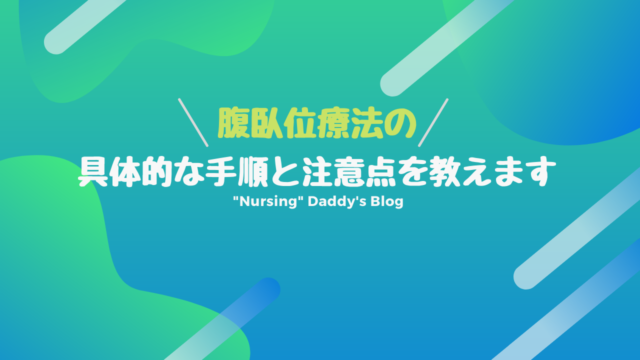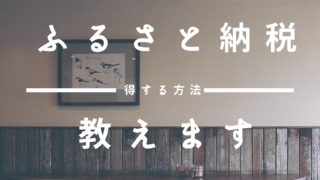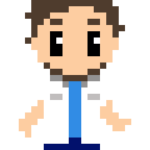昨今では特定行為研修を終えたナースやNP(診療看護師)と位置付けられるナースが増えています。
現場でもサラッとエコーを当ててアセスメントの材料にしている看護師をみかける場面もあるかと思います。
私自身たまに臨床でエコーを当てる訓練をしています。
そうするとナースステーションの隅からお姉様方の冷ややかな視線が・・
「あの人はミニドクターね。」
と、聞こえてきそうです・・笑
看護の現場ではミニドクターへのアンチテーゼというものが根強くあります。
現場でよく見られる・聞こえる点としては
- 看護師が医学知識をアセスメントに用いること
- 看護=清潔ケアをすること
- 医行為(診療の補助行為)を実践すること
などが多い印象があります。
確かに清潔ケアは患者のQOLを考える上では大事なケア介入です。
特に洗髪は僕自身も大好きで、患者さんからの希望があれば好んで実践します。
しかしながらどうでしょう?
そのケアって看護師の自己満足になっていませんか??
朝の全身清拭などのケアを実践した理由を述べられますでしょうか。
つまりとても重要な清潔ケアであっても、考えもなしに実践するのは好ましくないということです。
看護の専門性は患者のニードを把握し充足する介入を行い
健康の安寧を担保し促進をする。
そして患者の権利擁護(アドボケイト)を行う。
その他にもあると思いますがこうしたことだと考えています。
つまり清潔ケアをすることが看護ではなく、そのさきにある患者の健康やニーズを見据えることなのだと思います。
また、現場では看護師がリハビリすることなどに対しても
なんでも看護師がやるのはおかしい・・・
などという意見も聞かれます。
確かになんでもかんでも看護師が行うのはキャパオーバーになります。
ということで、こうした現場の背景には何があるのか
そして自分なりの解決策について述べていきたいと思います。

看護師の得意なこと苦手なこと
医療現場では日夜看護師が忙しく業務を行なっています。
看護師の業務って本当に煩雑、かつ多岐に渡ります。
一般の方がイメージする
- 注射(採血など)
- 薬の投与
- 検温
この他にも事務的な書類関係の処理や膨大な記録やチェックリスト
洗い物や薬の配薬やチェック、患者さんのベッド移動、家族対応などなど・・
あとは次の日の処方が切れていないかのチェック、医師への依頼もあります。
そして臨床業務だけでなく委員会などの事務作業。
これらを鳴り止まないナースコールやモニタアラームの中、効率よく処理しています。
そんな状況のなかで
患者さんにとって良いプラクティス(実践)が海外で明らかになり日本でも実践しようという流れがあります。
例えば集中治療関係で言えば早期離床(リハビリ)などです。
これらのプラクティスには大抵加算が付くようになるため現場ではリーダーや管理者がウチでもやるぞ!!と導入していきます。
これによって現場はどうなるか?
これまでの業務に加えて新たにリハビリを実践しなければならないのです。
ただでさえ残業していたのに、またか・・
という意見が聞こえてきそうです^^;
これはごもっともと言えます。
看護師の得意なことは良き実践を取り入れること
一方で苦手なことは業務を減らすことです。
患者さんにとって良き実践は取り入れるべきだし、提供されるべきだと思います。
しかし、なんでもかんでも看護師がやるというのは不可能な話です。
こうした状況を背景に
形だけの働き方改革で残業を厳しく取り締まられる。
もう理論的に破綻しています。
やはり重要かつ優先度の高いことは
看護師の業務を見直して慣習として行なっている不要な業務やケアなどを廃止していくことです。
タスクシフトを考えるべきなのは看護師の業務である
冒頭でもお伝えしましたが
タスクシフトといえば特定行為。
特定行為の本質は医師を待たずに、手順書をもとに看護師が判断してタイムリーに患者に医療を提供することです。
一方、医師のタスクシフトあるいはシェアをすることで医師の業務負担を軽減することも目的としてあります。
個人的にはタスクシフトするべきは看護師だと思います。
なぜならば看護師の業務の中には資格がなくてできる=誰でもできる業務が多くあるからです。
前述した看護師の専門性が発揮しきれない、そこに集中できないのは業務の煩雑さにあると思います。
だからこそ
新たな業務や看護師の役割拡大にも難色を示す状況が生まれます。
つまり抵抗するヒトが悪いのではなく
そのような思考を生ませた環境が悪いのだと思います。
本来の看護師のシゴトをするためには
現在行なっている誰でもできる業務を委託することが必要です。
つまり看護師もタスクシフトすべきということです。
コロナ禍で医療機関の運営における看護師の重要性に社会が気づけた今だからこそ、すぐにやるべきです。

私の実践例
こんな事をぬかしているアナタは何を実践しているんだ!
という声が聞こえてきそうなので^ ^;
本当に小さなことですが、自分の実践をお伝えします。(自分の病棟内)
自分は認定看護師であると同時に主任の立場です。
認定として早期離床(リハビリ)を促進したい!
という気持ちとは裏腹に
みんなの業務が手一杯なのはよく分かる。。
そこがジレンマでした。
そこで初めに私がとった行動は
- 何が業務を忙しくさせるか調査
- 要らない業務の抽出
- 要らない係の抽出
新たな取り組みを始める前に
減らせる業務や自動化できるもの
外部に委託できるものはあるのか
という視点で調査を始めました。
(スタッフへの聞き取り、管理者の考えを確認、他の部署の方法を確認)
係というのは病棟独自で取り組んでいることなどを割り振りするためのものです。
しかしながら
いつ誰がどのように決めたかは定かではなく
活動自体見えないものも多いのが現状でした。
そこで管理者である師長に係の削減を提案しました。
それと同時に削減によるデメリットも明らかにしてそれに対する代替え案もプレゼンしました。
業務に関してもシステムで自動化できるものを変えたり
ルチンで実施しているものを廃止
看護補助者への業務委託など
とにかく減らせるものは減らしました。
ちなみに係を減らした(統合したり)のは、最終的にリハビリを係としてすすめていくことを考えていたからです。
そしてリハビリを進めていく上では
- 係の人への教育
- リハビリの障壁を検討
- 取り組みの方法をスタッフと共に検討
- 係のメンバーの役割を決定
- 責任の所在が自分である事の説明
これを元に進め方やルールを決定し
- スタッフへの教育
- 意見募集期間を設定
- 質問などに対するフィードバック
- 開始
このように進めていきました。
これでも理解できない人がいるのは事実です。
組織論からもあるように、ある程度はいたしかたないと決めました。
周りが当たり前に実施する環境が作れればその人たちも自然にやるようになるからです。
開始してからは毎月のデータ集計と現場へのフィードバックは毎月実践しました。
時間が経つごとに意識が薄れていくのは想定していたので、定期的な教育のフォローアップをしました。
これによって5ヶ月くらいから安定したリハビリ実践がスタッフに根付くようになりました。
またこのリハビリに関してはシステマティックにできるよう医師も巻き込み、指示やプロトコルを活用していきました。
こうする事で、リーダーシップを図る人がいなくなった後も部署におけるリハビリの文化が定着するのではないかと考えています。
Quality Improvement(質の改善)
という視点で
患者にとって意味のある実践を病棟で取り組む。
これこそが本来の姿と思ってます。

ということで看護師のタスクシフトに関して述べました。
文章ばかりでつまらなかったらスミマセン^ ^;
最後まで読んでいただきありがとうございました!
この記事が参考になった方は是非シェアしてください♪
SNSのフォローもお願いします。